野生イタチが住宅街に現れる理由は?【餌と隠れ場所の豊富さ】家の周りの環境整備で、イタチの侵入リスクを軽減

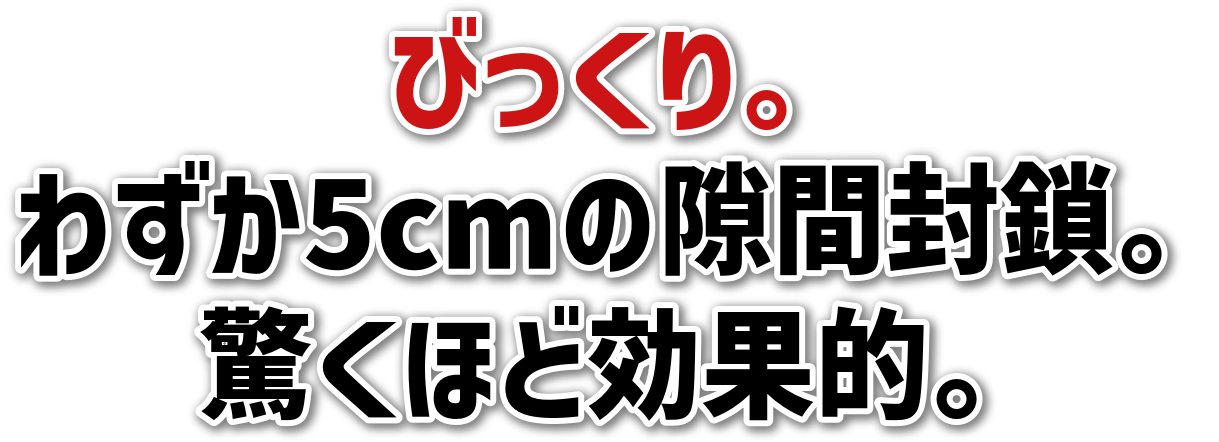
【この記事に書かれてあること】
夜中に庭でガサガサと音がしたり、朝起きたらゴミ袋が荒らされていたり…。- 住宅街はイタチにとって魅力的な環境
- 5cm程度の小さな隙間からも侵入可能
- 生ゴミの放置はイタチを引き寄せる要因に
- 都市化による自然habitat消失も影響
- 早めの対策でイタチとの共存を実現
そんな経験はありませんか?
実は、その犯人はイタチかもしれません。
野生のイタチが住宅街に現れる理由と、効果的な対策法をご紹介します。
イタチとの共存は可能なんです。
でも、放っておくと大変なことに…。
「うちの庭にイタチが来ないか心配」という方も、「もうイタチに困っている!」という方も、この記事を読めば安心できます。
さあ、イタチ対策のプロフェッショナルになる準備はできましたか?
野生イタチが住宅街に出没する背景

餌と隠れ場所が豊富!住宅街の魅力
住宅街は、イタチにとって天国のような環境なんです。なぜって?
餌と隠れ場所がたくさんあるからです。
「ここは楽園だ!」とイタチたちは喜んでいるかもしれません。
人間の生活圏には、イタチの大好物がごろごろ転がっているんです。
例えば:
- ゴミ置き場の生ゴミ
- 庭に遊びに来る小動物
- 果樹園の実
- ペットのえさ
「こんなにおいしいものが、毎日手に入るなんて!」とイタチは大喜びしているでしょう。
さらに、住宅街には隠れ場所もたくさん。
物置、倉庫、屋根裏、床下など、人目につきにくい場所がゴロゴロ。
イタチにとっては、安全で快適な住まいがそこら中にあるようなものです。
「ここなら、人間に見つからずに暮らせそう」とイタチは考えているかもしれません。
実際、多くの人は日中イタチを見かけることはありません。
夜行性のイタチは、人間が寝静まった後にこっそり活動するからです。
このように、住宅街はイタチにとって、食べ物も住まいも満足できる理想的な環境なんです。
だからこそ、野生のイタチがどんどん住宅街に引っ越してきてしまうというわけです。
小さな隙間から侵入!5cmの穴でも要注意
イタチは驚くほど小さな隙間から家に侵入できるんです。なんと、直径わずか5cmの穴があれば、スルスルっと入ってこられちゃいます。
「えっ、そんな小さな隙間から?」と驚く方も多いでしょう。
でも、イタチの体は柔らかくて細長いんです。
まるでゴムのように自在に形を変えられるので、人間には信じられないような小さな穴からも簡単に侵入できてしまうんです。
イタチが侵入しやすい場所は、例えばこんなところ。
- 屋根と壁の接合部の隙間
- 換気口や排水口
- 壁のひび割れ
- 窓やドアの隙間
- 配管や電線の通り道
イタチは優れた運動能力も持っているので、高い塀も軽々と乗り越えられちゃうんです。
侵入を防ぐには、家の外周を丁寧にチェックすることが大切。
5mm以下の隙間も見逃さないくらい細かくチェックしましょう。
「こんな小さな穴、大丈夫だろう」と油断は禁物です。
見つけた隙間は、イタチが噛んでも壊せないような頑丈な材料で塞ぐのがおすすめ。
金属製の網や板がいいでしょう。
こうして、イタチに「ここは入れないぞ」とあきらめさせることが大切なんです。
生ゴミの放置はNG!イタチを引き寄せる原因に
生ゴミの放置は、イタチにとって「いらっしゃ~い」と呼びかけているようなものです。その香りは、イタチの鼻をくすぐる魅力的な匂いなんです。
「え?そんなに臭いゴミ、イタチが好きなの?」と思うかもしれません。
でも、イタチにとっては最高のごちそうなんです。
特に肉や魚の残りかすは、イタチを引き寄せる強力な誘引剤になってしまいます。
イタチを寄せ付けないためには、こんな対策が効果的です。
- 生ゴミは必ず密閉容器に入れる
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- ゴミ置き場は清潔に保つ
- コンポストは蓋付きのものを使用する
- 庭に落ちた果物はすぐに拾う
でも、これらの対策を習慣化することが重要なんです。
イタチに「ここには餌がない」と思わせることが、侵入を防ぐ第一歩になります。
また、ペットのえさも要注意。
外に置いたままにしていると、イタチの格好のえさになってしまいます。
「ワンちゃん、食べ残しはダメよ」と言いながら、必ず片付けましょう。
生ゴミの管理は、イタチ対策だけでなく、衛生面でも大切です。
悪臭や害虫の発生も防げるので、一石二鳥の効果があるんです。
きちんと対策をして、イタチに「ここは餌場じゃないよ」とアピールしましょう。
都市化の影響で自然の生息地が減少中
イタチが住宅街に出没する理由の一つに、都市化による自然の生息地の減少があるんです。「イタチさん、ごめんね」と言いたくなるような状況なんです。
昔はイタチの楽園だった森林や草原が、どんどん開発されています。
「ぼくたちの家がなくなっちゃった!」とイタチたちは困っているかもしれません。
その結果、行き場を失ったイタチたちが、新たな生活の場を求めて住宅街にやってくるんです。
都市化がイタチに与える影響は、こんな感じです。
- 森林伐採による生息地の縮小
- 道路建設による生息地の分断
- 河川改修による水辺環境の変化
- 農地の宅地化による餌場の減少
- 光害や騒音による生活環境の悪化
確かに、イタチたちにとっては厳しい状況です。
でも、人間の生活も大切。
だからこそ、イタチとの共存を考えることが重要なんです。
例えば、都市計画の中に生態系への配慮を組み込むことが必要です。
緑地や公園を適切に配置したり、野生動物の移動経路を確保したりすることで、イタチたちの生活空間を守ることができます。
また、私たち一人一人ができることもあります。
庭に在来種の植物を植えたり、小さな池を作ったりすることで、イタチを含む野生動物の生息環境を少しずつ改善できるんです。
都市化は避けられない流れですが、人間とイタチが共に暮らせる環境づくりを目指すことが大切なんです。
そうすれば、「ここなら人間もイタチも幸せに暮らせそう」という場所が増えていくはずです。
イタチ対策は早めが肝心!放置は逆効果
イタチ対策、早めに始めることが超大切なんです。「まあ、いいか」と放っておくと、あっという間に大問題に発展しちゃうんです。
イタチの被害を放置すると、こんな悲惨な結果になりかねません。
- 家屋の損傷がどんどん進行
- 糞尿による悪臭が部屋中に充満
- 衛生状態が悪化し、家族の健康被害も
- イタチが繁殖して大規模な群れに
- 近隣全体の生活環境が著しく悪化
でも、これは現実に起こりうる事態なんです。
イタチは繁殖力が強く、あっという間に数が増えてしまいます。
だからこそ、イタチの気配を感じたらすぐに対策を始めることが重要です。
例えば、家の周りの点検を定期的に行い、侵入口になりそうな場所を見つけたら即座に塞ぐ。
庭の整備を行って、イタチの隠れ場所をなくす。
生ゴミの管理を徹底するなど、できることから始めましょう。
「でも、イタチがかわいそう」と思う人もいるかもしれません。
確かに、むやみに駆除するのは良くありません。
しかし、適切な対策を取ることは、人間とイタチの両方にとって良いことなんです。
イタチにとっても、人間の生活圏は本来の生息地ではないんです。
早めの対策は、イタチにとっても「ここは住みにくいな」と感じさせ、自然の生息地に戻るきっかけになります。
そうすれば、イタチも人間も、お互いの生活圏を尊重しながら共存できるんです。
イタチ対策、面倒くさいと思わずに、今日から始めてみましょう。
「よし、やるぞ!」という気持ちが、快適な生活環境を守る第一歩になるんです。
住宅街vs自然環境 イタチの生息地選択

森林と住宅街 イタチはどちらを好む?
イタチは本来、森林を好む動物ですが、最近では住宅街も魅力的な環境になっているんです。「えっ、イタチって森の動物じゃないの?」と思う人も多いでしょう。
確かに、イタチの本来の生息地は森林です。
木々が生い茂り、小動物がたくさんいる環境が、イタチにとっては理想的だったんです。
でも、最近の住宅街は、イタチにとって意外と住みやすい環境になっているんです。
なぜでしょうか?
それは、こんな理由があるからです。
- 餌が豊富(ゴミ置き場や庭の小動物など)
- 隠れ場所が多い(物置や屋根裏など)
- 天敵が少ない(大型の捕食動物がいない)
- 年中安定した気温(冬も暖かい)
森林では、季節によって餌の量が変わったり、天敵に襲われる危険があったりします。
でも、住宅街では年中安定した生活が送れるんです。
「ここなら安心して暮らせるぞ」とイタチは考えているかもしれません。
ただし、これは人間にとっては困った状況です。
イタチが増えすぎると、家屋への被害や衛生面での問題が出てきます。
でも、イタチを無闇に追い払うのも良くありません。
大切なのは、イタチと人間が共存できる環境づくりです。
例えば、家の周りをきれいに保ち、イタチが侵入しやすい場所をなくすことが重要です。
そうすれば、イタチも「ここは住みにくいな」と感じて、自然の森に戻っていく可能性が高くなります。
イタチと人間、お互いが快適に暮らせる環境を目指すことが、これからの課題なんです。
農村部と都市部 イタチの生息数の変化
昔は農村部に多かったイタチですが、最近では都市部でもよく見かけるようになってきました。この変化には、驚くべき理由があるんです。
「えっ、イタチって田舎の動物じゃないの?」と思う人も多いでしょう。
確かに、昔はそうでした。
農村部には畑や田んぼがたくさんあり、イタチの大好物であるネズミや小鳥がいっぱいいたんです。
まさに、イタチにとっては天国のような環境でした。
でも、最近では状況が変わってきています。
イタチの生息数の変化を見てみると、こんな傾向があります。
- 農村部:徐々に減少傾向
- 都市部:増加傾向
その理由は、主に3つあります。
- 農村部の環境変化(農薬の使用増加、耕作放棄地の増加)
- 都市部の緑地増加(公園や街路樹の整備)
- 都市部の食料廃棄物の増加(ゴミ置き場や飲食店の裏など)
特に都市部では、思わぬところがイタチの楽園になっています。
例えば、繁華街の裏通り。
人間にとっては暗くて怖い場所かもしれませんが、イタチにとっては絶好の狩り場なんです。
飲食店から出る生ゴミや、そこに集まるネズミたち。
イタチにとっては、まさに「美味しいレストラン」が立ち並んでいるようなものです。
でも、この変化は人間にとっては悩ましい問題です。
都市部でイタチが増えすぎると、家屋への被害や衛生面での問題が出てきます。
かといって、むやみに駆除するのも生態系のバランスを崩す恐れがあります。
大切なのは、イタチと人間が共存できる環境づくりです。
例えば、都市部でも緑地を増やしつつ、ゴミの管理を徹底する。
そうすることで、イタチにとっても人間にとっても住みやすい環境が作れるんです。
イタチの生息数の変化は、私たちの生活環境の変化を映し出す鏡。
これからの街づくりを考える上で、大切なヒントを与えてくれているのかもしれません。
河川敷vs住宅街 イタチの好みは?
イタチは河川敷と住宅街、どちらが好きなのでしょうか?実は、両方とも大好きなんです。
でも、最近では住宅街の方がより好まれる傾向にあります。
「えっ、イタチって水辺の動物じゃないの?」と思う人もいるでしょう。
確かに、イタチは泳ぎが得意で、河川敷は昔からの定番の生息地でした。
魚やカエル、水辺の小動物がたくさんいて、イタチにとっては理想的な環境だったんです。
でも、最近では住宅街の方が人気上昇中。
なぜでしょうか?
それは、こんな理由があるんです。
- 年中安定した食料(ゴミ置き場や庭の小動物)
- 安全な隠れ家(物置や屋根裏)
- 天敵が少ない(大型の捕食動物がいない)
- 温暖な環境(冬でも暖かい)
河川敷では、季節や天候によって餌の量が変わったり、増水時には危険があったりします。
一方、住宅街では年中安定した生活が送れるんです。
「ここなら安心して子育てできるぞ」とイタチは考えているかもしれません。
ただし、これは決して河川敷が住みにくくなったわけではありません。
むしろ、両方の環境を上手に使い分けているんです。
例えば、こんな具合です。
- 春?秋:河川敷で活動的に狩りをする
- 冬:住宅街で暖かく過ごす
- 子育て時期:安全な住宅街を選ぶ
この傾向は、私たちに重要なメッセージを伝えています。
河川敷と住宅街、どちらの環境も大切にしなければいけないということです。
河川敷の自然を守りつつ、住宅街での共存方法を考える。
そうすることで、イタチと人間が調和して暮らせる環境が作れるんです。
イタチの生息地選択は、自然と都市の調和を考える上で、大切なヒントを与えてくれているのかもしれません。
人間との接触頻度 住宅街での共存リスク
住宅街に住み着いたイタチ。人間との接触頻度が増えると、思わぬリスクが生まれることがあるんです。
でも、適切な対策を取れば、イタチと人間の平和な共存も可能なんです。
「えっ、イタチと人間が出会うことってあるの?」と思う人もいるでしょう。
実は、意外と多いんです。
特に住宅街では、イタチと人間の生活圏が重なるため、接触のチャンスが増えています。
では、どんな場面で接触が起こりやすいのでしょうか?
主に次のような状況が考えられます。
- 夜間のゴミ出し時
- 庭での作業中
- 屋根裏や物置の掃除時
- 夜間のペットの散歩時
ただし、イタチは基本的に臆病な動物です。
人間を見ると、すぐに逃げてしまうことが多いんです。
でも、餌を求めて大胆になることもあるんです。
特に、子育て中のメスイタチは、食料確保のために冒険することもあります。
そんなイタチと人間が接触すると、どんなリスクがあるのでしょうか?
主に次の3つが考えられます。
- 噛みつきや引っかき傷(防衛本能から)
- 病気の感染(まれですが、狂犬病などの可能性)
- 精神的ストレス(突然の遭遇によるショック)
でも、大丈夫です。
適切な対策を取れば、これらのリスクは大幅に減らすことができます。
例えば、こんな対策が効果的です。
- 夜間のゴミ出しは明るい時間帯に変更
- 庭の整理整頓(イタチの隠れ場所をなくす)
- 定期的な家屋点検(侵入経路を塞ぐ)
- ペットの餌は戸外に放置しない
「人間もイタチも、お互いの生活圏を尊重しよう」という気持ちが大切なんです。
イタチと人間の共存は、決して不可能ではありません。
むしろ、お互いを理解し、適切な距離を保つことで、豊かな生態系の一部として共に暮らしていけるはずです。
そんな未来を目指して、一緒に考えていきましょう。
季節による生息地の変化に注目!
イタチの生息地は、季節によってくるくる変わるんです。この変化を理解すると、イタチ対策がぐっと効果的になります。
さあ、イタチの季節の旅を覗いてみましょう!
「えっ、イタチって引っ越しするの?」と思う人もいるでしょう。
そう、まさに季節ごとの引っ越しなんです。
イタチは賢い動物で、季節に合わせて最適な環境を選んでいます。
では、季節ごとのイタチの好みの場所を見てみましょう。
- 春:繁殖期で、暖かく安全な場所(屋根裏や物置など)
- 夏:涼しい場所(河川敷や森林の木陰)
- 秋:食料が豊富な場所(果樹園や農地の近く)
- 冬:暖かい場所(住宅街や都市部)
特に注目したいのは、春と冬の住宅街への接近です。
春は子育ての時期。
安全で暖かい屋根裏は、イタチママにとって理想的な育児室なんです。
冬は寒さを避けるため、人間の生活圏の暖かさに引き寄せられます。
この季節変化を理解すると、効果的な対策が立てられます。
例えば:
- 春:屋根裏や物置の点検と補強
- 夏:庭や畑の管理(果物や野菜の収穫忘れに注意)
- 秋:落ち葉の早めの処理(隠れ場所をなくす)
- 冬:家の隙間や穴の補修(侵入防止)
ただし、気をつけたいのは地域差です。
北国と南国では、イタチの行動パターンが少し異なる場合があります。
例えば:
- 北国:冬の住宅街滞在が長く、春の繁殖期が遅めに
- 南国:冬でも外で活動的、住宅街滞在は短め
イタチの季節による生息地の変化を知ることは、私たちの生活にも大きなヒントを与えてくれます。
自然の中で生きる動物たちの知恵を学び、人間も季節の変化に寄り添った暮らし方を考える。
そんなきっかけにもなるんです。
「よし、イタチの季節カレンダーを作って、対策を立てよう!」そんな気持ちになったら、あなたはもうイタチ博士の仲間入りです。
季節の変化を楽しみながら、イタチとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
イタチの住宅街侵入を防ぐ5つの対策法

隙間封鎖作戦!5mm以下の穴もチェック
イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。なんと、5mm以下の穴さえあれば、スルスルっと入ってきちゃうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く人も多いでしょう。
でも、イタチの体は細長くて柔らかいんです。
まるでゴムのように自在に形を変えられるので、人間には信じられないような小さな穴からも簡単に侵入できてしまうんです。
では、どんなところを重点的にチェックすればいいのでしょうか?
ここに注目です。
- 屋根と壁の接合部
- 換気口や排水口
- 窓やドアの隙間
- 配管や電線の通り道
- foundation(建物の土台)のひび割れ
隙間を見つけたら、どう対策すればいいでしょうか?
ここがポイントです。
- 金属製の網や板で塞ぐ
- 耐候性のあるコーキング剤で埋める
- 専用の隙間テープを貼る
確かに、一度に全てを完璧にするのは難しいです。
でも、少しずつでも対策を進めることが大切なんです。
例えば、週末ごとに家の外周をゆっくり歩いて、隙間をチェックする。
「あれ?ここに小さな穴があるぞ」と見つけたら、すぐに対策する。
そんな習慣をつけることで、少しずつイタチの侵入を防ぐことができるんです。
隙間封鎖は、イタチ対策の基本中の基本。
「よし、今週末はイタチ探偵になって、家中の隙間を探してみよう!」そんな気持ちで取り組んでみてください。
きっと、思わぬ発見があるはずです。
生ゴミは完全密閉!匂い漏れゼロが目標
生ゴミの匂いは、イタチにとって「いらっしゃ~い」と呼んでいるようなものです。この匂いを完全に遮断することが、イタチ対策の重要なポイントなんです。
「えっ、そんなに匂いが大事なの?」と思う人もいるでしょう。
実は、イタチの嗅覚は人間の約40倍も敏感なんです。
私たちが気づかない微かな匂いでも、イタチにとっては強烈な誘惑になってしまうんです。
では、どうやって生ゴミの匂いを遮断すればいいのでしょうか?
ここが大切です。
- 密閉容器の使用:蓋がしっかり閉まる容器を選ぶ
- 二重包装:生ゴミを新聞紙で包んでから袋に入れる
- 冷凍保存:生ゴミを冷凍庫で保管し、収集日に出す
- 消臭剤の活用:重曹やコーヒーかすを活用する
- こまめな処理:生ゴミを溜めずに毎日処理する
でも、これらの対策を習慣化することが重要なんです。
例えば、密閉容器の使用。
最初は「めんどくさい」と思っても、毎日続けていると自然に習慣になります。
「ああ、今日も匂いゼロだな」と満足感を感じられるようになりますよ。
また、生ゴミの冷凍保存は、匂い対策だけでなく衛生面でもメリットがあります。
カビや虫の発生も防げるので、一石二鳥の効果があるんです。
「よし、今日から生ゴミ対策マスターになるぞ!」そんな気持ちで取り組んでみてください。
きっと、家族みんなで協力して楽しく続けられるはずです。
匂い漏れゼロの達成は、イタチ対策の大きな一歩になるんです。
光と音でイタチ撃退!センサーライトの活用法
イタチは、突然の光や音が大の苦手。この弱点を利用して、センサーライトを活用すれば、効果的にイタチを撃退できるんです。
「え?そんな簡単な方法があるの?」と驚く人も多いでしょう。
実は、イタチは臆病な性格。
予期せぬ光や音に遭遇すると、びっくりしてすぐに逃げ出してしまうんです。
では、どうやってセンサーライトを効果的に使えばいいのでしょうか?
ここがポイントです。
- 設置場所:イタチの侵入経路に向けて設置
- 感度調整:小動物でも反応するよう調整
- 光の強さ:できるだけ明るく、広範囲を照らす
- 点灯時間:長めに設定(30秒以上がおすすめ)
- 定期的なメンテナンス:電池交換や清掃を忘れずに
大丈夫です。
最近のセンサーライトは、光の方向や強さを細かく調整できるんです。
近隣に配慮しつつ、効果的に使うことができます。
センサーライトの活用は、音との組み合わせでさらに効果アップ!
例えば、こんな方法があります。
- 風鈴をセンサーライトの近くに吊るす
- 動物の鳴き声を録音したスピーカーと連動させる
- ガラガラと音のする物(小石入りペットボトルなど)を置く
でも、こういった複合的な刺激が、イタチを効果的に撃退するんです。
センサーライトの設置は、夜間のセキュリティ対策にもなります。
イタチ対策と防犯対策、一石二鳥の効果が得られるんです。
「よし、今週末はセンサーライト博士になるぞ!」そんな気持ちで取り組んでみてください。
きっと、家族で相談しながら最適な設置場所を見つける過程も、楽しい思い出になるはずです。
天然ハーブの力!イタチが嫌う香りで対策
イタチは特定の香りが大の苦手。この特性を利用して、天然ハーブの力でイタチを寄せ付けない環境を作ることができるんです。
「えっ、ハーブでイタチが逃げるの?」と驚く人も多いでしょう。
実は、イタチの嗅覚は非常に敏感。
私たちには心地よい香りでも、イタチにとっては強烈な刺激になることがあるんです。
では、どんなハーブがイタチ撃退に効果的なのでしょうか?
ここがポイントです。
- ペパーミント:清涼感のある強い香り
- ラベンダー:リラックス効果のある香り
- ローズマリー:爽やかでスパイシーな香り
- タイム:ハーブティーでおなじみの香り
- セージ:独特の強い香り
具体的な活用法はこんな感じ。
- ハーブを鉢植えで庭に置く
- 乾燥ハーブを袋に入れて侵入経路に置く
- ハーブオイルを水で薄めてスプレーする
- ハーブティーを冷ましてジョウロで撒く
実は、これらのハーブは虫除けにも効果があるんです。
イタチ対策と虫除け、一石二鳥の効果が得られるんです。
ただし、注意点もあります。
ペットがいる家庭では使用に注意が必要です。
中には、猫や犬にとって有害なハーブもあるので、事前に確認することが大切です。
また、ハーブの効果は永続的ではありません。
定期的な手入れや植え替えが必要になります。
でも、それも楽しみの一つ。
「今日はどのハーブの香りを楽しもうかな」と、季節ごとに変化を楽しむこともできるんです。
「よし、我が家をハーブの楽園にしよう!」そんな気持ちで取り組んでみてください。
きっと、イタチ対策だけでなく、心地よい香りに包まれた暮らしを楽しめるはずです。
庭の整備が重要!餌場にならない環境づくり
庭はイタチにとって魅力的な餌場になりかねません。だからこそ、庭の整備がイタチ対策の重要なポイントなんです。
「えっ、庭にそんな餌があるの?」と驚く人も多いでしょう。
実は、イタチは雑食性。
果物や野菜はもちろん、小動物や昆虫まで、庭にはイタチの大好物がたくさんあるんです。
では、どんなポイントに注意して庭を整備すればいいのでしょうか?
ここが大切です。
- 落ち葉や枯れ枝の除去:小動物の隠れ家をなくす
- 果樹の管理:落果を放置しない
- コンポストの適切な管理:蓋付きの容器を使用
- 鳥の餌台の適切な設置:イタチの手の届かない高さに
- 水たまりの解消:虫や小動物を寄せ付けない
でも、これらの作業は定期的な庭の手入れとして少しずつ行えばいいんです。
例えば、週末のたびに家族で庭の掃除をする習慣をつける。
「今日は何個の落ち葉を集められるかな?」と、子どもと競争しながら楽しく掃除するのもいいですね。
また、庭の構造を工夫することで、イタチが寄り付きにくい環境を作ることもできます。
例えば:
- 砂利や小石を敷き詰める:イタチが歩きづらい地面に
- 背の低い植物を選ぶ:隠れ場所をなくす
- フェンスの下に金網を埋める:穴掘りを防ぐ
- 照明を適切に配置:夜間の活動を抑制
でも、こういった工夫が、イタチを寄せ付けない効果的な方法なんです。
庭の整備は、イタチ対策だけでなく、美しい庭づくりにもつながります。
「よし、今年こそ近所一番の素敵な庭にするぞ!」そんな気持ちで取り組んでみてください。
きっと、イタチ対策と庭づくりの両方を楽しめるはずです。